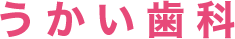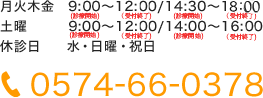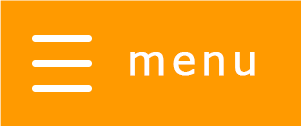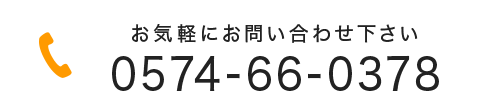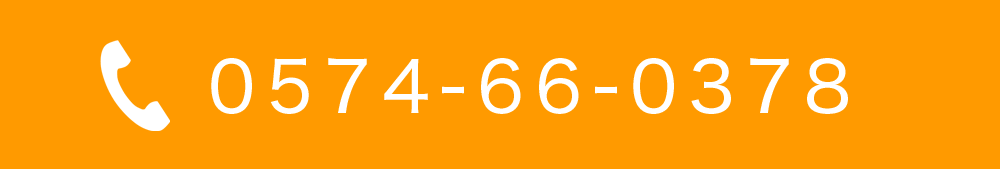『うかい歯科の感染予防対策について】
皆様、こんにちは。院長の鵜飼です
ふたたび新型コロナウィルスの感染拡大で毎日、大変な思いをしている事と思います。
当院では、患者様に安心して治療を受けていただく為、『更なる』コロナ対策として下記の対策を新たにしておりますのでお伝えします。
まずは、以前にもお伝えしましたが、治療中のエアロゾル感染防止の為、各チェアー毎に口腔外バキュームを用意しております。
また消毒、除菌を徹底する為に
① オゾン発生器『オースリークリア3』
② フィリップス UV-C殺菌用デスクライト
を新たに設置する事にしました
---------------
① オゾン発生器『オースリークリア3』とは
診療室全体をオゾンの力で除菌する装置です
オゾンとは、太陽からの有害な紫外線を吸収して、地上に住む我々を守ってくれる「オゾン層」のことです。オゾンは大気中に自然に存在する気体分子であります。
特徴として、発生したオゾンの全量が、別な物質と結びついて分解されていきます。
臭いのもととなる物質を分解したり、ウイルスを分解したりと、有害物質をどんどん分解してくれるのですが、インフルエンザウイルス、ノロウイルス、ロタウイルス などにも効果があります。
放置しておくと分解して酸素となりますので、塩素等と異なり残留による危険を心配する必要はありません 。
② フィリップス UV-C殺菌用デスクライト
待合室や消毒室は昼休憩と診療後に『フィリップス UV-C殺菌用デスクライト』
を照射しております。
この殺菌効果は下記を参考にしてください
• 【あらゆる細菌・ウイルスを不活性化】 フィリップス UV-C殺菌用デスクライトは、カビ、バクテリアのほか、あらゆる細菌やウイルスを短時間で効果的に不活性化する製品です。
• 【UV-Cライトで35年以上の実績】 当社は、35年以上にわたりUV-C アプリケーションの専門的技術を蓄積してきました。これにより、適切な安全設計のもと、様々なアプリケーションで使用可能な幅広いUV-Cランプおよび照明を提供することができます。
• 【ボストン大学研究所にて有効性確認】 ボストン大学国立新興感染症研究所(NEIDL)で行った実験レポートによると、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を植菌した物体の表面にフィリップス UV-Cライトを照射した場合、5mJ/cm2のUV-C照射量(曝露時間6秒)で、表面についた新型コロナウイルスの99%を不活性化できることが分かりました。
ーーーーーーーー
今回のコロナの件が起きる前から、当院では基本的な消毒はもちろんの事、たびたびネットニュースでも話題になる、治療器具、歯を削る機械の滅菌も、10年以上前から患者様毎に毎回 高圧蒸気滅菌をしています。
その為に、普通なら『1台』しかないオートクレーブが当院は『3台』あります。
なぜなら患者様毎に毎回 治療器具、歯を削る機械を滅菌しようとすると、どうしてもオートクレーブが『3台』必要になるからです。
(詳細については待合室に写真つきで案内しております)
また、『手袋』『マスク』『ゴーグル』はもちろんですが、今回のコロナは無症状の方も多いとの事から、知らないうちに感染している可能性もある為、さらに予防として『フェイスシールド』『エプロン』をして治療をしております。
感染拡大を防止する為に、場合によっては治療を先に延期していただく事もあります。
ご迷惑をかける事もありますが、何卒ご理解、ご協力をお願いします。