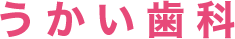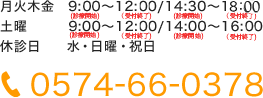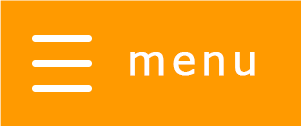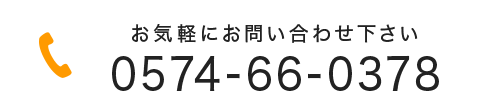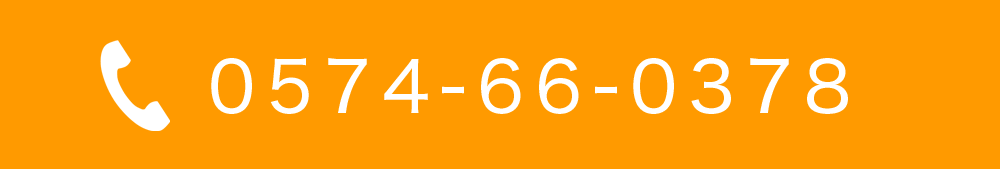痛みがなくなってラッキ-! は大間違い
2021.11.20更新
痛みがなくなってラッキ-! は大間違い
【歯の神経が大切なワケ】
むし歯が進行してひどい痛みを感じている場合には「神経をとりましょう」と提案させていただくことがございます。
痛みを感じる神経をとれば、当然痛みはなくなるわけですが、そこには大きなデメリットが。
今回は、歯の神経と役割について解説します。
【歯髄(神経)の役割って】
「痛みを感じるためだけなら、神経なんてない方がいい…」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このセンサーこそ歯髄の大切な役割!「痛み」や「しみる」といった感覚があるからこそ、むし歯に早く気づくことができます。
さらに、むし歯が一定の部分まで達すると、「痛み」や「むし歯の進行」を抑えるために、歯の内側に壁を作って刺激が伝わりにくくなるように働いてくれるのです。
また、歯髄には栄養を運んでくれる血管が通っているので、丈夫な歯を保つためにも重要な役割があります
【やむを得ず神経をとらないといけない場合も・・・】
むし歯ができても大切な神経を残せるように、歯科医院では治療に最善を尽くしています。
しかしながら、むし歯が大きくなって神経を傷めている場合などには、やむを得ず神経をとらなければなりません。
実は「神経だけをとる治療」はとても難しく、海外では医療費が高額なため「神経だけをとることができずに抜歯するケース」もあります。
日本の場合は、保険診療を使って神経だけをとり除き、歯を残す治療が可能になっています。
【神経をとるとどうなるの?】
神経をとると痛みを感じにくくなりますが、その後むし歯にならないわけではありません。
むしろ、神経をとった歯はむし歯になっても気がつきにくいので、発見を遅らせないためにも定期検診が必要不可欠です。
定期的にしっかりチェックをしてもらいましょう。
投稿者: