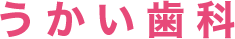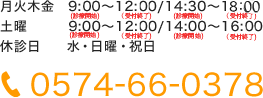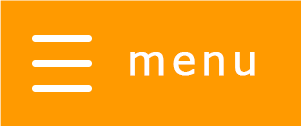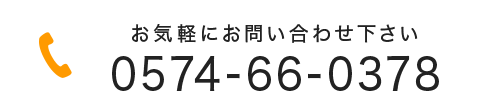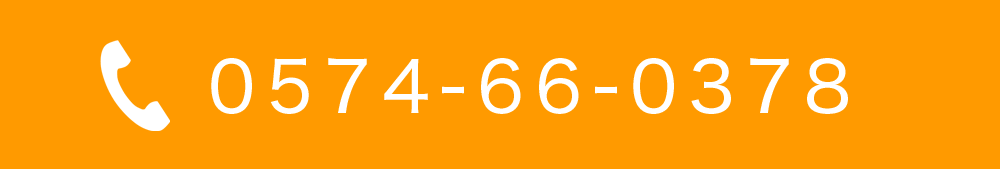【つめものの常識、非常識】
2021.06.16更新
【つめものの常識、非常識】
【これだけある!つめものが取れる原因】
食べ物を噛んだり、だ液で常に湿っていたり、食事のたびに酸性・アルカリ性が入れ替わったりと、お口の中は想像以上に過酷な環境です。
そのため、長く使い続けたつめものには歪みやヒビが入り、歯の形と合わなくなると取れてしまうことも。
また、銀歯などの金属製のつめものをつけるとき、歯科用セメントにより合着されますが、それは時間とともに劣化します。
このセメントが溶けて無くなることで、隙間が空いてつめものは取れてしまうのです。
他にも、歯ぎしりや食いしばり、継続して強い力が加わる、などが原因で、つめものが取れることがあります。
【最悪の場合! 再び虫歯に…】
つめものは高い精度で製作されていますが、取れるほどではなくても、隙間ができることは多々あります。
そして、この隙間にプラーク(歯垢)が入り込むと、新たなむし歯を引き起こしてしまうのです。
こうしたリスクがあるため、治療したところほどしっかりケアをする必要があります。
【つめものが取れたまま放置したらどうなるの?】
痛みがないと、つい放置してしまいがちですが、つめものが外れてしまった歯の面はでこぼこしているため、歯みがきがしづらく、汚れがたまりやすいもの。
つめものが取れたままでいるとあっという間にむし歯が進んでしまうので注意が必要です。
そのうえ、つめものが外れた部分は象牙質が露出している場合がほとんど。
象牙質はむし歯になりやすい組織なので、つめものが取れたらすぐに歯医者さんに行くのがおすすめです。
早めに対応すれば取れたつめものをそのまま再着できることもあるので、早めに歯科医院で診てもらいましょう!
投稿者: