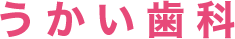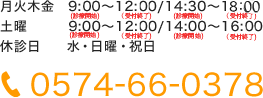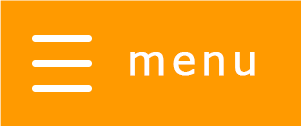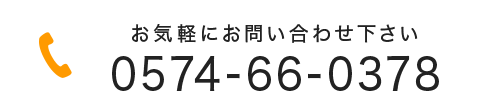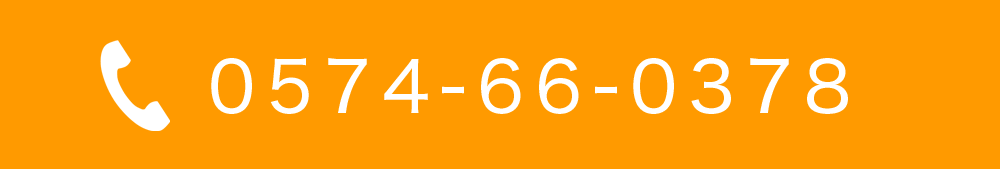大掃除
2023.12.01更新
こんにちは。院長の鵜飼です。
12月の風物詩といえば大掃除。
「ちょっと面倒だな」と思うこともあるかもしれませんが、やはりきれいなお家で迎える新年は気持ちのよいものです!
ところでこの大掃除、実は『煤払い(すすはらい)』という神事が、その由来といわれています。
煤払いは、新年に年神様をお迎えするための行事で、「家中の煤を払ってきれいにしておくと、年神様がご利益を持って降りてくる」と、考えられていました。
一年のスタートを気持ちよく迎えられると、その年は何か良いことが起こりそうな予感がするのも、古くから受け継がれてきた「日本人ならではの感覚」によるものかもしれません。
さて、何かと忙しいこの時期ですが、みなさんは「お口の大掃除」も済んでいますか?
歯科医院という場所は、むし歯や歯周病といった「困りごと」がないと、つい足も遠のいてしまいがちです。
しかし、お口の中もお部屋と同じで、日ごろから定期的にきれいにしておくことが大切。
ぜひ、お家もお口もすっきりさせて新しい年を迎えましょう!
投稿者: